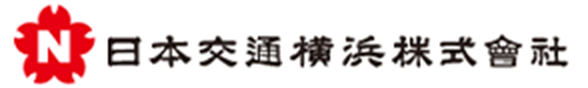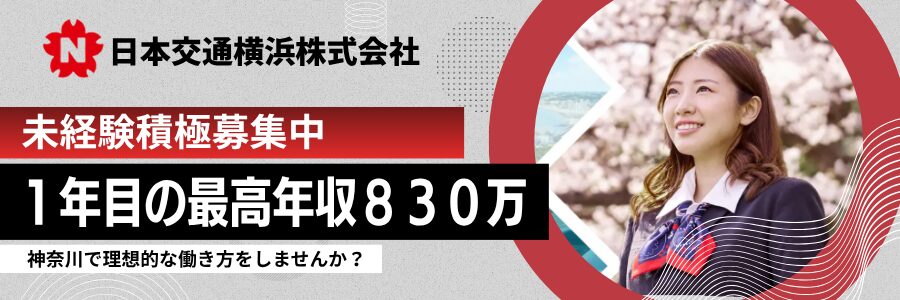「タクシー運転手の夜勤は本当にきついのか?」──そんな疑問をお持ちの方へ。この記事では、現役ドライバーのリアルな声をもとに、夜勤勤務の実態や体調管理の工夫、夜勤でも無理なく働くためのヒントを日本交通グループの日本交通横浜が監修のもと解説します。夜勤への不安を少しでも和らげ、安心して働ける一歩を踏み出すための参考にしてください。

古川 篤志
【日本交通横浜㈱ 統括本部長】
2006年に都内日交グループ会社ワイエム交通㈱へ乗務員として入社。現場経験を積みながら運行管理者、代表取締役を歴任し、2021年からは日本交通グループ関西の執行役員本部長として勤務。2023年より日本交通横浜㈱に異動し、現在は統括本部長として会社全体の運営と採用に力を入れています。
運行管理者(旅客)の資格を持ち、採用担当としては5年間で年間230名の採用、年間142名の面接を経験。現場と経営の両方を知る立場から、これからタクシードライバーを目指す方々に安心して入社いただける環境づくりを心がけています。
タクシー運転手の夜勤とは?働き方の特徴を解説

夜勤勤務の時間帯とスケジュールの基本
タクシー運転手の夜勤は、一般的に「夕方18時頃から翌朝5時頃まで」の時間帯を指します。実働時間は会社によって異なりますが、拘束時間はおよそ10〜12時間程度が一般的です。この時間帯は、仕事帰りのサラリーマンや終電後の移動、深夜の飲食業従事者の帰宅など、一定の需要があります。
夜勤では、日中と違って交通量が少ないため、運転に集中しやすい一方で、深夜特有の眠気との闘いや安全面への注意が求められます。特に0時〜3時の間は、身体の体温と集中力が最も下がるとされる「魔の時間帯」とも言われており、この時間帯をどう乗り越えるかが、夜勤継続のポイントです。
隔日勤務との違いとは
タクシー業界では、「夜勤専門勤務」と「隔日勤務」がよく比較されます。隔日勤務とは、1回の勤務が朝から翌朝(例:8時~翌2時)または夕方からお昼前(例:15時~翌9時)で、その後1日は必ず明休(明け休み)がある制度です一方で夜勤専門勤務は、夜間のみの短縮勤務となるため、生活リズムの作りやすさという点では夜勤のほうが自分に合っているという方も多くいます。
夜勤専従の方が勤務時間が安定している一方、隔日勤務は連勤が少なく休日が多いといったメリットもあります。どちらが向いているかは、生活スタイルや体調管理のしやすさによって異なります。
夜勤ドライバーに求められるスキルと注意点
夜勤ドライバーには、安全運転技術に加え、「集中力の持続」「臨機応変な対応力」が求められます。深夜帯は酔客や急病人の対応が増える時間帯でもあり、冷静かつ迅速な判断力が欠かせません。また、防犯意識の高さやトラブル回避能力も重要です。
最近では、車内防犯カメラの設置や、タクシーアプリ「GO」などでの配車が主流になっており、不特定多数の乗客を拾うよりも指名に近い乗車が多く、以前よりリスクは減ってきています。
どんな人が夜勤に向いているのか
夜勤は、規則正しい生活が苦手な方よりも、自分のペースで動けることに魅力を感じる人に向いています。例えば、日中に自由時間が欲しい方、稼げる時間帯を狙って効率的に働きたい方などです。
一方、生活リズムが崩れやすい体質の人や、暗所や孤独が苦手な方には向かないケースもあります。そのため、まずは体験乗務や短期勤務などで自分との相性を確認してみるのもおすすめです。
夜勤が「きつい」と言われる4つの理由
生活リズムが乱れやすい
夜勤勤務の大きなハードルのひとつが、昼夜逆転による生活リズムの乱れです。人間の体内時計は日中の活動に最適化されており、夜間に働くことは本来のリズムと逆行します。そのため、日中に十分な睡眠を取るのが難しく、慢性的な寝不足に陥りやすくなります。
特に自宅が日当たりの良い場所や生活音の多い環境にあると、深い睡眠がとりづらくなり、結果的に体力・集中力の低下に繋がるケースもあります。遮光カーテンや耳栓などで対策を取っているドライバーも多く見られます。
体調を崩しやすい・疲労がたまりやすい
夜勤では、自然な眠気との戦いに加え、長時間座ったままの運転によって身体への負担が大きくなります。肩こりや腰痛、目の疲れなどが蓄積しやすく、適切な休憩やストレッチを取り入れなければ慢性疲労の原因にもなります。
さらに、勤務前後の食事時間が不規則になりがちで、消化器系への負担も増えます。夜勤を継続する上では、バランスのとれた食事や軽い運動など、日常のセルフケアが非常に重要になります。
深夜帯ならではのトラブル対応
深夜のタクシー運転では、酔っ払いや寝落ちした乗客、支払いトラブルなどに直面することがあります。日中よりも客層に注意が必要な時間帯とも言われており、精神的なストレスや対応力が求められます。
防犯カメラの設置やアプリ配車の導入により、リスクは年々低減しているものの、夜間の単独運行では常に安全意識を持ち、冷静な対処ができることが求められます。
精神的なストレスと孤独感
夜勤では人と接する機会が限られ、孤独感や疎外感を覚えることがあります。特に新人ドライバーにとっては、夜の静けさや会話のない時間が精神的な負担となることも。こうしたメンタル面の負荷も、「夜勤はきつい」と言われる一因です。
一方で、夜の落ち着いた街並みや深夜の空気を心地よいと感じる人もおり、感じ方には個人差があります。孤独をプラスに捉えられる性格かどうかが、夜勤の適性を分けるポイントになるかもしれません。
夜勤でも安心して働ける3つの体調管理術

睡眠の質を上げる生活習慣の工夫
夜勤勤務を続けるうえで最も重要なのが「質の高い睡眠を確保すること」です。たとえ睡眠時間が短くなったとしても、深く眠れるかどうかが疲労回復に直結します。
睡眠の質を上げるためには、以下のような習慣が効果的です。
- 日中に寝る前は、遮光カーテンやアイマスクで光を遮断
- 耳栓やホワイトノイズを活用し、生活音をカット
- 寝る1時間前にはスマホやテレビを控え、副交感神経を優位にする
- カフェインやアルコールの摂取は就寝2〜3時間前までに控える
特に、毎回寝る前に同じ行動(歯磨き、白湯、ストレッチなど)をする“就寝ルーティン”を決めると、脳が「これから眠る」と認識しやすくなり、寝つきが良くなります。
食事と運動で体調をキープ
不規則な勤務時間でも、食事と運動のリズムを意識的に整えることで、体調の乱れを防ぐことができます。夜勤中は特に胃腸への負担が大きくなるため、以下の点に注意しましょう。
- 消化に良いものを中心に摂取する(おかゆ・うどん・野菜スープなど)
- 深夜のドカ食いは避け、分食スタイルでエネルギー補給
- 朝帰宅後は胃腸にやさしい軽食にとどめ、睡眠を優先する
- 休日には軽いウォーキングやストレッチで代謝を維持
小さなことの積み重ねが、体力の持続や免疫力の維持に大きく関わってきます。
社内制度や福利厚生の活用方法
安心して夜勤を続けるためには、会社の支援制度や福利厚生をしっかり活用することも大切です。たとえば、日本交通横浜では以下のような制度があります。
- 健康診断や運転前の点呼・アルコールチェックの徹底
- シャワー室・仮眠室・休憩室など、夜勤明けに嬉しい設備
- 生理休暇や家族都合の調整など、柔軟なシフト運用
- 同乗研修やチーム制度によるサポート体制
体調に不安を感じたときでも、すぐに相談できる環境があることで、安心して勤務を継続できます。
- 入社準備支度金30万円支給!
- 入社後半年「月給38万」の給与保証あり!
- 月間出勤回数「12~13回」のみ!
現役ドライバーの本音に学ぶ夜勤のメリットとやりがい
高収入を目指せるチャンスが多い
夜勤勤務の最大の魅力のひとつが、稼ぎやすさです。深夜割増料金(22時〜翌5時)は通常料金の2割増しで設定されており、同じ走行距離でも日勤より効率よく売上を上げることができます。
さらに、金曜日や週末、イベント開催日などは深夜帯に乗客が集中するため、需要のピークを狙って稼働することで売上アップが見込めます。「短時間でしっかり稼ぎたい」という方にとって、夜勤は好条件がそろった働き方です。
夜の街は渋滞が少なく運転しやすい
夜間は交通量が少なく、都市部でもスムーズに走行できることが多いため、運転のストレスが少ないという声もよく聞かれます。日中に比べて信号待ちや渋滞に悩まされる場面が減り、目的地まで効率的に乗客を送迎できるため、運転に集中しやすい環境が整っています。
特に横浜エリアでは、深夜でも主要駅や繁華街からの帰宅需要が安定しており、効率良く仕事ができる時間帯でもあります。
アプリ配車や法人需要で安定収入も可能
最近では、タクシーアプリ「GO」などを通じたアプリ配車の利用が増えており、深夜帯でも事前予約やアプリからの自動配車で、待機時間なく次々と乗客を獲得できる仕組みが整っています。
また、夜間に出勤・帰宅する法人契約の社員送迎や、飲食業スタッフなどの移動ニーズも根強く、一定のリピート利用があるため、売上の安定性という点でも夜勤にはメリットがあります。
お客様との深いコミュニケーションがある
夜勤では、1人のお客様との移動時間が長くなる傾向があります。そのため、「静かに休みたい方」「悩みを話したい方」など、さまざまな心情と向き合う場面が生まれやすいです。
現役ドライバーからは、「終電を逃したお客様が安堵してくれたとき」「介護帰りの家族の気持ちに寄り添えたとき」など、感謝の言葉にやりがいを感じる瞬間が多いという声もよく聞かれます。
夜勤でも無理なく続けるための働き方改善アイデア
家族との時間を確保するための工夫
夜勤に対する不安の中でもよくあるのが「家族とのすれ違い」です。しかし、日中が空く夜勤勤務では、子どもの送り迎えや平日昼間の家族時間が取りやすいというメリットもあります。
たとえば、夜勤明けの午前中に仮眠をとり、午後は家族と過ごすスタイルを確立しているドライバーも少なくありません。家族の理解を得るためにも、あらかじめシフトの見通しや体調管理の工夫について共有しておくと安心です。
職場環境やサポート体制を見極める
夜勤勤務を継続するには、会社のサポート体制や職場の風土も大きな影響を与えます。たとえば、以下のような環境が整っている職場は、夜勤にも安心して取り組みやすいです。
- 同乗研修やOJT制度がある
- 管理者が常駐しており、トラブル時に相談しやすい
- 防犯設備やセキュリティ体制が整っている
- 夜勤明けにリフレッシュできる休憩施設がある
特に未経験者にとっては、「夜勤をひとりでこなせるか」という不安が大きいもの。入社前に会社説明会や職場見学などを通じて、サポート体制の有無をしっかり確認しておくことが大切です。
自分のペースに合った会社選びのポイント
夜勤がきついかどうかは、「会社選び」によって大きく変わります。業務量・勤務時間・福利厚生・サポート体制・社内の雰囲気など、自分にとって働きやすい環境が整っているかどうかを見極めましょう。
たとえば、日本交通横浜では
- 完全シフト制で勤務調整がしやすい
- 月給保証制度があるため収入面も安心
- 女性ドライバーや主婦層も多数在籍し、職場の柔軟性が高い
といった特徴があります。夜勤に不安がある方こそ、「どんな会社で働くか」が働きやすさを左右する重要な要素となります。
まとめ
タクシー運転手の夜勤は、生活リズムの乱れや体調管理の難しさ、深夜ならではのトラブルなど「きつい」と感じる要因がいくつかあります。しかし、実際に夜勤で働く現役ドライバーの声からは、高収入の可能性や運転しやすさ、静かな時間に集中できるメリットも数多く聞かれます。
また、睡眠や食事の工夫、社内制度の活用、家族との調整などによって、夜勤でも無理なく長く働ける環境を整えることは可能です。勤務スタイルの柔軟性や会社選びも、夜勤の働きやすさを左右する大きなポイントになります。
もし夜勤への不安がある方は、まずは自分の生活に合ったペースで働ける職場を選び、段階的に夜勤を取り入れてみるのも一つの方法です。「夜勤=きつい」と決めつけず、実情を知ったうえで自分に合った働き方を見つけてみてください。